1659年(万治2年)~ 享保2年4月28日(1717年6月7日)
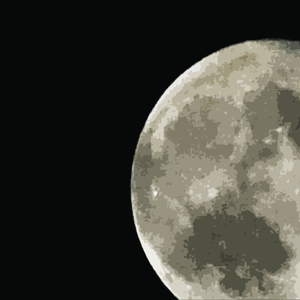 蕉風を受け継ぐ流派のひとつに伊勢派があり、その重鎮に岩田涼菟の名がある。芭蕉が神宮参拝の折に入門したと言われる、晩年の門人である。
蕉風を受け継ぐ流派のひとつに伊勢派があり、その重鎮に岩田涼菟の名がある。芭蕉が神宮参拝の折に入門したと言われる、晩年の門人である。
近松門左衛門とも接点があったと見られ、「曾根崎心中」の道行の文句には、偶然居合わせた涼菟の呟きが採用されたとの話も伝わる。真偽の程は定かではないが、それがあの「夢の夢こそ哀れなれ」である。
はたしてこの人は、夢に生きたひとなのかもしれない。ある春、近所の桜を見ようと草履履きで出たのはいいが、京都東山・播州須磨寺を巡って、長崎にまで行ってしまったという逸話がある。
病中吟に「今までは人が病むぞと思ひしにわが身の上にかくの仕合」とあるあたり、事実を肯定できず、夢の中に真実を求めて彷徨った人のように思う。
辞世は「合点じやそのあかつきの子規」。「合点」は、納得の意味よりも俳諧の評点と見た方がいい。そうすれば「あかつきの子規」の姿が、自ずと明確になる。
この辞世にも逸話があって、息を引き取る間際まで「暁のその子規」にしようか「その暁の子規」にしようか迷っていたという。それを、盟友の乙由が「この期に及んで何の迷いがあるか、その暁の子規」と声を荒げて決した。
いずれにせよ、死に臨んで涼菟が認識した己の姿は、暁のホトトギス。古来歌われてきたホトトギスには様々な意味付けがなされるが、「暁のホトトギス」と言った場合には、いの一番に鳴くことが強調される。
つまり、平談俗語を新風として確立し、伊勢派の礎となったこと、それを暁のホトトギスになぞらえた。そして死の間際に初めて、その事実を見つめ、自らの人生に合格点をつけた・・・
乙由は、暁のホトトギスたる涼菟に続くものがあるだろうかと、「何鳥ぞ此跡鳴ぞほととぎす」の追悼句を寄せている。
因みに涼菟は、「ほととぎすほととぎすとて寝入りけり」という句も残している。死に接するまでのホトトギスは、夢をいざなう存在でこそあったのだろう。
いま涼菟の辞世を口遊めば、後徳大寺左大臣の有名な歌「ほととぎす鳴きつる方を眺むればただ有明の月ぞ残れる」が思い出される。暁のホトトギスは、西の空を漂う月となったのかもしれない。
寝る人は寝させて月は晴れにけり 涼菟
岩田涼菟に関する補足
1)岩田涼菟 ⇒ 資料1
2)伊勢派 ⇒ 涼菟が伊勢俳壇の神風館の名号を継承し、中川乙由と合流した一派。卑俗でわかりやすい俳諧が特徴であったが、各務支考の美濃派とともに「支麦の徒」などと呼ばれて蔑まれた。
3)芭蕉 ⇒ 松尾芭蕉
4)曾根崎心中 ⇒ 近松門左衛門の代表的な世話物浄瑠璃。「此の世のなごり 夜もなごり 死に行く身をたとふれば あだしが原の道の霜」で始まる道行の文句が有名な、心中ものである。
5)ほととぎす鳴きつる方を眺むればただ有明の月ぞ残れる ⇒ 千載集。小倉百人一首第81番。
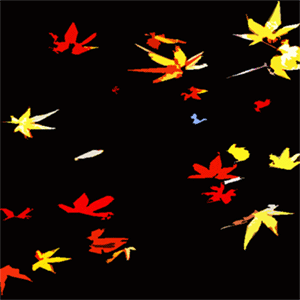 「おくの細道」の旅で、加賀の茶商でもある小杉一笑に会うことを楽しみにしていた松尾芭蕉。一笑は、貞享年間に蕉門を叩いた新参者ではあったが、貞門・談林では名を馳せた人。
「おくの細道」の旅で、加賀の茶商でもある小杉一笑に会うことを楽しみにしていた松尾芭蕉。一笑は、貞享年間に蕉門を叩いた新参者ではあったが、貞門・談林では名を馳せた人。 現代では、顧みられることも少なくなった女流俳人・久保より江。しかし、煌びやかなしづの女・久女の時代にあってさえ、この女性の右に出るものはいなかった。小説の世界では夏目漱石や泉鏡花などが取り上げ、白蓮との華麗な交流も知られている。
現代では、顧みられることも少なくなった女流俳人・久保より江。しかし、煌びやかなしづの女・久女の時代にあってさえ、この女性の右に出るものはいなかった。小説の世界では夏目漱石や泉鏡花などが取り上げ、白蓮との華麗な交流も知られている。 芭蕉が、「先徳多か中にも、宗鑑あり、宗因あり、白炭の忠知ありなん」(初蝉集)と慕った俳人が居る。江戸時代にあって、「木枯らしの言水」と並ぶ渾名を得ながらも、現在では、切腹して果てた俳人として名を残す神野忠知。
芭蕉が、「先徳多か中にも、宗鑑あり、宗因あり、白炭の忠知ありなん」(初蝉集)と慕った俳人が居る。江戸時代にあって、「木枯らしの言水」と並ぶ渾名を得ながらも、現在では、切腹して果てた俳人として名を残す神野忠知。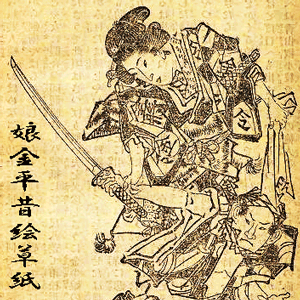 その人物は、「俳諧名家全伝」(桃李庵南濤1897年)に「謹厳で毫も行を乱さず」とあるように、非常に厳格な人物だったと思われる。江戸時代末期には、「破枕集」に「白炭はやかぬむかしの雪のえだ」を見つけた柳亭種彦が、似たもの同士が絡み合う勧善懲悪本、「娘金平昔絵草紙」の善なる主人公に仕立て上げた。それを鳴雪が自叙伝の中で取り上げたことから、現代にも名を残す存在とはなった。
その人物は、「俳諧名家全伝」(桃李庵南濤1897年)に「謹厳で毫も行を乱さず」とあるように、非常に厳格な人物だったと思われる。江戸時代末期には、「破枕集」に「白炭はやかぬむかしの雪のえだ」を見つけた柳亭種彦が、似たもの同士が絡み合う勧善懲悪本、「娘金平昔絵草紙」の善なる主人公に仕立て上げた。それを鳴雪が自叙伝の中で取り上げたことから、現代にも名を残す存在とはなった。